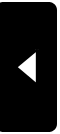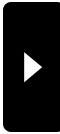2015年03月15日
本町若連 水窪町奥領家本町 三嶽一郎建造の浜松型一層唐破風大屋台


本町若連 水窪町奥領家
浜松型一層唐破風大屋台
昭和四十九年(1974)建造
大工 三嶽一郎
彫刻 浦部一郎
奥領家本町若連は八幡若連と共に八幡神社の氏子である。
みさくぼ祭は奥領家小畑諏訪神社、地頭方向市場春日神社と奥領家神原八幡神社の祭禮を合同で行っている。
本町の屋臺は浜松で重層御殿屋台を数多く手掛けた三嶽一郎の作。






浜松重層御殿屋台の祖三嶽駒吉の技を受継いだ三嶽一郎は昭和二十五年の田町を皮切りに十三台の浜松型重層御殿屋台を手掛けた。

三嶽一郎大工は父である三嶽駒吉棟梁と共に戦前の浜松重層御殿屋台の建造に携わったという。現存する最古の浜松型重層入母屋造御殿屋台である二俣横町叉水連の屋台建造にも、二俣に逗留して携わっていたようだ。その形は三嶽御殿屋台の原点となっているようである。

倭魂社 笠井上町
昭和五十三年建造
大工 三嶽一郎
彫刻 浦部一郎
笠井の倭魂社は大工、彫刻ともに本町若連と同一の姉妹屋台になる。
三嶽一郎氏が手掛けた浜松型一層唐破風大屋台は、この二台だけのようだ。

三嶽四代目工匠早川真匠は、平成八年に三嶽流の一層唐破風屋台を復活させた。

水窪の屋臺は女性の小太鼓が外側を向いて左右に並ぶ。

花火も打ち上げられ、祭りは非常に賑やかだ。

後輪外車は浜松型屋台の特徴の一つでもある。元々三嶽駒吉がこの形式を得意としたということだろう。
DVD『天龍の屋臺』に収録!!
2015年03月14日
八幡若連 水窪町奥領家神原 先代八まん連 浜松まつり最古の一層唐破風屋台


八幡若連 水窪町奥領家神原
浜松型一層唐破風大屋台
昭和五年(1930) 浜松市八幡町八まん連建造
大工 岡田五左衛門 豊川市牛久保
彫刻 浦部一郎 浜松市利町(豊橋市出身)
昭和三十五年(1960) 八幡若連へ譲渡
大正十一年(1922)に、五社神社が浜松市の総社となり、それまで季節の風物詩であった濱松名物の凧揚が、初めて五月四日の五社神社祭典と結び付き、祭禮行事として執り行われるようになった。


江戸末期に二俣で曳かれていた屋臺
浜松にも明治末期頃から底抜け屋台が登場してはいたが、江戸時代から屋臺を曳く掛塚や二俣、明治期には本格的な屋臺を建造している(当時は浜松市外で会った)天王や雄踏、遅くとも大正期には本格的な屋臺が登場している笠井や宮口、根堅などに比べると、浜松の本格的な屋台の登場は遅く、昭和の時代を迎えてからである。

昭和五年建造の野口町先代屋台(現・浜北区貴布祢みゆき連)
昭和に入ると、五社神社の神輿は凧揚げ会場まで渡御し、会場からの曳き揚げに際しては総社神輿が先頭で還御し町々の屋臺が続くという神輿還御行列が行われるようになったようだ。
大正十四年の時点で、二俣諏訪神社祭典では十台の大屋臺が諏訪神社神輿に随行する神輿渡御が行われており、当時は浜松からも多くの見物客が二俣を訪れていた。
神輿渡御、還御という神事に随行する屋臺としては、底抜け屋台は具合が悪い。
当時の二俣では、神事である渡御に随行する大屋臺は女人禁制であり神聖な存在で、花屋台(底抜け屋台)で渡御行列に加わることは禁じられていた。また、神輿を二階から見下ろすことは不敬とされていた。
昭和十一年の『静岡民友新聞』には、浜松総社神輿渡御の際「若衆が・・・二階乃至三階から神輿を拝してゐた民家数軒に乱入・・・」とあるのは、二俣の例に倣ってのことであろう。
神輿渡御、還御の神事を始めるにあたって二俣を参考にした、というのは当時の二俣と浜松の経済の結び付きの強さを考えれば自然な成り行きである。その後、二俣も浜松に倣って桃山式二層花屋台を導入しており、相互に影響を与えていたとみてよい。
神輿渡御随行に相応しい本格的大屋臺の建造が望まれたというのは当然の成り行きで、昭和五年建造の八幡町と野口町の一層唐破風大屋台が、その始まりだと云われている。

現存する最古の浜松型重層入母屋造御殿屋台 二俣横町叉水連
昭和八年頃には鴨江町大工三嶽駒吉によって、初めて浜松型重層入母屋造御殿屋台が建造され、次々と大型屋臺が登場する。当時の御殿屋台は女人禁制で、お囃子も異なり、屋臺を威勢良く若衆が曳き廻していたようだ。
残念ながら、戦前の浜松五社神社祭典で曳き廻された豪華絢爛な御殿屋台は浜松空襲で全て焼失。
三嶽駒吉の重層入母屋造御殿屋台は叉水連と春野町西領家坂下紅葉社の二台のみが現存している。

八幡町と野口町の浜松型一層唐破風大屋台も戦禍を逃れ現存している、戦前の浜松五社神社祭典を知る貴重な屋臺である。
重層入母屋造御殿屋台に比べ、一層唐破風屋台は組みばらしが容易であった点が戦禍を逃れた要因の一つかもしれない。
八幡、野口の屋台は共に、豊川市牛久保の岡田五左衛門が建造した。岡田家は三河大工の筆頭であったと云い、江戸時代には立川和四郎と共に仕事をしていたという。
彫刻の浦部一郎は、この頃豊橋から浜松へ移り住み、遠州で最初の仕事が、この八幡と野口の屋台の仕事であったようだ。

昭和十年(1935)浜松鴨江町大工三嶽駒吉建造の浜松型一層唐破風大屋台、天竜区横山町朝日連
浜松型一層唐破風大屋台の特徴は堂々とした大型の唐破風、背は低いが横幅は広い。細部は掛塚の様式よりも二俣に近い、といった点が挙げられる。
戦後、掛塚の屋台大工が御殿屋台建造も多く手掛けたため、いつの間にか浜松の屋台を「掛塚式」などと云うようになってしまったが、本来は浜松独自の形式の屋台であり、重層御殿屋台の祖は浜松鴨江の大工三嶽駒吉であることは忘れてはならない。
また、三河からの影響も掛塚以上に色濃いものであったことを考慮したい。
正式な掛塚型一層唐破風本舞台は、馬込町奴組など数台しか浜松まつりには登場していない。

八まん連では、昭和三十五年に八幡若連に先代屋台を売却後、三年間は屋臺曳き廻しを休止し昭和三十八年に高塚房太郎大工による現屋台を建造。重層御殿屋台では数少ない総漆塗りの屋臺となっている。

みさくぼ祭は、全国的に有名な仮装コンテストもあり、夜の屋台曳き廻しも大変賑やかで露店も数多く出ている。風情のある街並と露店の建ち並ぶ風景は、古き佳き時代の日本の祭りそのものだ。

水窪では女性の小太鼓が左右外側を向いて並ぶ独特のスタイル。
水窪は平家の落人が隠れ住んだ里であり、京美人の遺伝子を受継いでいるので美人が多いそうだ。

屋台がすれ違う際には、お囃子バトルが見られる。
本町若連の屋台も三嶽一郎建造の浜松型一層唐破風大屋台。
DVD『天龍の屋臺』に収録!!
2015年03月13日
八王社 春野町篠原 神楽の里「勝坂」紅葉の「明神峡」 神仙世界の入口(春野町豊岡)


八王社 春野町豊岡地区篠原
御所車型二輪屋台
若い曳き手が多く威勢の良い曳き廻しを見せる春野町豊岡地区篠原の八王社。
八王子神社の祭典で曳き廻すと共に、夜は平木八幡連同様、気田の街へと繰り出し、祭りの夜の気田の賑わいに華を添える。

明治九年(1876)に篠原、勝坂、山路西東、植田の各村が合併して豊岡村が発足。
明治二十二年(1889)に気田、宮川、石切、小俣京丸と豊岡が合併して気多村となった。


豊岡地区は神楽の里として知られる勝坂、紅葉の名所明神峡を含む広大な面積に集落が点在する。


春から秋にかけて、国道362号線で篠原を通り過ぎてから杉川を渡って左手に別れ県道389号線に入り小石間トンネル(全長700メートルの一車線トンネルで中央付近の待避所以外では自動車のすれ違いが出来ない)を抜ければそこは神仙世界の入口である。


県道389号水窪森線は、狭隘で落石が多く危険であるということで、勝坂~門桁~河内浦間で19時~翌朝5時30分の夜間全面通行止めとなっている。
まさに神仙の暮らす秘境である。


とはいえ、篠原は賑やかな気田の街に隣接しており、国道362号線も面しているため、お祭りは非常に賑やかだ。
小石間トンネルを抜けた野尻(豊龍社)、植田(豊栄社)にも屋臺がある。
篠原から山を登った赤岡(赤栄社)にも屋臺があるが曳き廻しを休止している。
DVD『天龍の屋臺』に収録!!
2015年03月12日
八幡連 春野町平木


八幡連 春野町平木
御所車型二輪屋台
平木の八幡(やわた)連は、平木八幡神社祭典で曳かれる屋台だが、夜は気田南宮神社祭典の屋台と合流し、気田の街まで屋台を曳いていく。

八幡連、気田の四台に加え篠原八王社も合流し、気田の街に六台の屋台が揃う。
天竜区の山間部に、これだけ豪華な屋臺が集結して派手に祭典を行っている、という事実は一部の祭りファン、屋臺ファンを除いてあまり知られていないが、この他に宮川地区で四台、杉地区で一台の計十一台の屋臺が旧気多村地区で同時に曳き廻されている。

平木村は明治九年(1876)に、河内村、高瀬村、久保田村、里原村、夜川十五七百村と合併し宮川村が発足。
明治二十二年(1889)に気田村、宮川村、豊岡村、小俣京丸村、石切村が合併して気多村となる。

平木は宮川地区であるが、祭典時は宮川地区の屋台(春野文化センターに高栄社、久栄社、天神社が集結する)とは合流せず、平木大橋を渡って気田へ合流している。

春野地区の二輪屋台は前方中央に補助輪を設けているケースが多い。
また、浜松など天竜川以西の四輪屋台に多く見られる連名の入った小田原提灯を、御所車型二輪屋台にもぶら下げているケースも多い。
DVD『天龍の屋臺』に収録!!
2015年03月10日
天神社 春野町里原 一層唐破風二輪屋台


天神社 春野町里原
一層唐破風二輪屋台
春野町宮川地区里原天神社祭典で曳き廻される天神社の屋台は堀之内地区の鷹尾連、龍勢社、八面社、気田の金勢社と同じ一層唐破風の二輪屋台で、春野町独特の屋臺形式の一つ。
元々が四輪屋台であった鷹尾連、龍勢社、金勢社は二輪屋台としては異例に大型の屋台であり、また腰から上の形式は遠州型四輪屋台に準じたものである。
八面社はやや小ぶりだが、囃子台は擬宝珠高欄で囲まれた舞台屋臺の形式をとっている。

これに対し天神社は前方に出高欄のついた御所車型二輪屋台の形式で屋根のみ唐破風となった珍しい形状の屋臺になっている。

一目で天神社とわかる個性的な屋臺。

茶畑をゆったりと進んでいく屋臺。
DVD『天龍の屋臺』収録!!
2015年03月06日
久栄社 春野町久保田 日本一の大天狗面


久栄社 春野町久保田
一層唐破風大屋台
春野町宮川地区、久保田諏訪神社祭典で曳き廻される久栄社の屋臺は、地元大工による建造。
後輪外車の四輪屋台で、前後御簾脇に彫刻が入り、春野らしい個性的な屋臺。

しっかりとした彫刻が入っている。

前面に御簾が降り、欄間部分に内幕が巻かれている。

天狗の橋を渡っていく屋臺

前夜、宮川地区の屋台が大天狗面のある春野文化センターに集結。
翌日の早朝6時30分に久栄社は屋臺を曳いて文化センターに向かい、前夜の清掃を開始。
貴重な大天狗面と屋臺のツーショット!!
DVD『天龍の屋臺』に収録!!
2015年03月04日
高栄社 春野町高瀬


高栄社 春野町高瀬
二層高欄二輪屋台
熊野神社祭典で曳き廻される春野町宮川地区高瀬高栄社の屋臺は北領社などと同じく春野型と云っても良い二層高欄二輪屋台。
上下の高欄が朱に塗られ、細身に作られた屋臺は立ち姿が美しく非常に個性的。
春野の屋臺らしく腰板の杢目もなかなか美しい。

上高欄が擬宝珠高欄であるのも春野の屋臺の特徴。
人形は森町の亀八
先代屋台は気田金川金勢社の先代屋台を譲り受け、非常に大きく立派な屋台であったとのことだが、伊勢湾台風で屋台小屋と共に倒壊してしまったという。
その後、現在の屋臺を新造している。
DVD『天龍の屋臺』に収録!!


高瀬の大天狗面のお隣、柳澤食堂さんで『天龍の屋臺』DVD販売中!!

2015年03月02日
北領社 春野町西領家原 秋葉山本宮秋葉神社門前 二段欄間の二層高欄二輪屋台


北領社 春野町西領家原
二層高欄二輪屋台
建造年代不詳
春野町西領家原の北領社は二層高欄の二輪屋台で、欄間は二段。
所謂、森や掛川の御所車型二輪屋台と異なり、遠州四輪屋台に近い特徴を持っている。


二段欄間は明治期の犬居鷹尾連、龍勢社と二俣諏訪連(現水ヶ谷連)、西古連(現万斛西)、叉水連(現金勢社)と吾妻連に共通し、掛塚型一層唐破風本舞台には見られない特徴。
鷹尾連、龍勢社、吾妻連は御簾脇障子を有するが、これも掛塚型一層唐破風本舞台には見られない仕様である。


龍山村瀬尻で大正初期建造という鳴鶴軒、明治二十八年建造という二段欄間の東組といった中泉の二輪屋台も御所車型ではなく二層高欄二輪屋台だが、基本形は横須賀の禰里に近い。


江戸末期に二俣で曳かれていた金屋台(現雄踏領家金館車)の二階部分を取り去って二輪に改造すれば北領社のような二層高欄の形状に近い。金屋台、北領社共に上高欄は擬宝珠高欄となっている。

これも旧犬居町の屋台の特徴に準じているが、天井は横桟に板が渡されただけで吹き抜け状態である。

金屋台の一階部分天井も同様に板が渡されているだけである。

江戸末期から明治前期に二俣に存在した金屋台は後世まで豪華絢爛な様が語り草となっており、近隣(天竜川水系の水運全盛時には現在以上に二俣と気田川流域には密接した関係があったと思われる)の屋臺文化に大きな影響を与えていることは間違いないだろう。

東領家和田之谷の東和連子供屋台
犬居地区では龍勢社、鷹尾連、有聲舎にも二層高欄二輪の子供屋台があり、このことからも森の御所車型二輪屋台の影響を受ける以前に独自の屋臺文化が天竜川水系を通じて入ってきたのではないだろうか。

二層高欄四輪屋台の先代気田中栄社(現磐田市下万能松尾社)も明治中期建造で二段欄間の屋台であり、二俣、犬居の屋台との関連性が感じられる。
秋葉山には超一流の宮大工が出入りしており、国産最高峰の気田欅の産地であった春野町の屋臺文化は非常に興味深いものがあるが、史料が少なく解明されていない部分が多い。


正一位県社秋葉山本宮秋葉神社下社の隣に鎮座する領家村社六所大明神
秋葉神社下社は山頂にあった秋葉山神社が昭和十八年に全焼(全国的に火防で知られるのは秋葉寺に祭られる三尺坊大権現であり、秋葉神社の御祭神火之迦具土神は火によって焼き払い浄化する火神である)し、六所大明神の隣に秋葉神社下社が造営された。
最初にこの地に鎮座していたのは六所大明神である。
屋臺は秋葉神社の門前を通過していくが、秋葉神社の祭典ではなく六所神社祭典の屋臺曳き廻しである。
DVD『天龍の屋臺』収録!!
2015年03月01日
芳川町大橋 芳組 (先代白糸連) 浜松まつり最古の屋台


芳組 南区芳川町大橋
二俣型一層唐破風大屋台
大正十四年(1925)二俣白糸町建造
大工 遠山鶴雄
平成元年(1989)芳川町大橋が購入
例年、浜松まつりの御殿屋台曳き廻しに参加する屋台の中で、最も古く、唯一の大正年間建造の屋台であり、大正十四年に二俣白糸町白糸連の大屋台として建造された。

とは言え、浜松市内には、江戸時代建造とされる屋台も残っており、二俣新町(南がく連)が江戸時代末期に曳いていた二階建ての金屋台は十八世に紀掛塚で建造という説もある。現西区雄踏町宇布見領家の金館車。

やはり江戸末期に二俣町車道(㡌山連)が曳いていた三階建ての名古屋型見舞車。
文政四年(一八二一)尾張國愛知郡廣井村下花車町の先代二福神車として建造。現在は浜北区宮口研精社が所有。

天竜区二俣町鹿島西煙火連の屋台は安政三年(一八五六)三河國宝飯郡三谷村仲屋敷で建造。
大正十三年(一九二四)赤佐村根堅大門が購入し改造。
平成元年、西煙火連が購入、平成二十年、西鹿島大工太田良彦棟梁により復元新調。
この他にも江戸末期から明治前期の建造と推定される屋台が雄踏中村館車と天竜区に複数存在する。

雄踏小山館車は明治二十二年、長上郡天王村大工齋藤太代吉が建造。浜松の二層御殿屋台の祖型ではないかと云われている。
現浜松市域では、良質の木材が豊富にあり、秋葉光明信仰で宮大工も多数いた天竜区域が林業、養蚕、鉱山の好況に支えられ、天竜川水運により江戸文化の伝播も早く、最初に屋臺文化が花開いている。
明治末期に現遠州鉄道が西鹿島まで開通すると、二俣の屋臺文化や祭禮囃子が遠鉄沿線に広まっていった。
明治末期頃から簡易的な底抜け屋台が凧揚げ会場への道中に曳かれ出したという浜松凧揚げまつりは、大正十一年から五社神社祭典となり、昭和五年、浜松にも本格的な屋台が初めて登場した。先代八幡町八まん連(現天竜区水窪八幡若連)、野口町の組(現浜北区貴布祢みゆき連)屋台は豊川牛久保の岡田五左衛門の作。

西伊場町の屋台は昭和七年、西伊場町大工奥田光国、石黒九一、神久呂村志都呂の大工稲垣皆吉の三人によって建造された。彫刻は元魚町の浦部一郎。奥田、稲垣両大工は昭和九年に磐田郡龍川村横山町市場の三華連屋台建造にも携わっている。
屋台は浜松まつり(当時は五社神社祭典)の為に建造されたわけではなく、西伊場賀茂神社祭典で曳き廻すために建造された。


浜松まつりに重層入母屋造御殿屋台が登場したのは昭和八年と云われる。然し、戦前建造の重層御殿屋台は浜松空襲により、当時の浜松市内にあったものは全て焼失した。
浜松重層御殿屋台の祖三嶽駒吉が建造した屋台で現存するのは二俣横町叉水連と春野町西領家坂下紅葉社のみ
。


東領家和田之谷東和連大屋臺
昭和二年(一九二七)建造
大工 遠山鶴雄
彫刻 伊藤松次郎(彫松)
天幕 日本橋白木屋
芳組屋台(先代二俣白糸連)を建造した白糸町大工遠山鶴雄は昭和二年に磐田郡犬居町(現天竜区春野町)東領家和田之谷の東和連屋台も建造。昭和二年には二俣繭市場の取引高が日本一となり、北遠一帯は林業と共に養蚕による好況を迎えていた。
戦前、天竜区域以外で建造された屋台の多くが檜、杉を主材料としていたのに対し、天龍の屋臺は欅材が多用されている。
東和連の屋臺には杢目が美しい国産最高峰の気田欅が使用され、彫松の彫刻が前後御簾脇にも配されている。

当時の二俣は通りが狭く、白糸連大屋台は柱間を四尺五寸と細身に作ってあり、現在の大型な浜松御殿屋台の中ではやや小ぶりだが、照り起りの美しい唐破風と細身のフォルムは独特の存在感を放っている。

白糸町は当時の二俣町中心部からやや外れた、明治中期まで田畑ばかりの新興町であり、屋臺本体は完成させたものの鬼板などは昭和五十三年頃まで絵板であった。昭和末期に鬼板彫刻を一新、腰彫りを追加した。


曲線で構成される二俣型唐破風は、垂木の加工も難しい。老朽化のため補強の金物が使われているが、オリジナルの遠山鶴雄の精緻な作り込みは素晴らしい出来。

元々は四輪内車であったが、芳組では浜松の屋台に多い後輪外車に改め、屋根に銅板を葺き彫金などを追加している。
浜松まつりだけでなく、十月の津毛利神社祭典でも屋台を曳き廻す。浜松まつりと津毛利神社祭典ではお囃子も異なっている。
DVD『諏訪神社祭典 地之巻』収録!!
2015年02月28日
白糸連 本町 豊田佐吉が憧れた十基紡『遠州二俣紡績』


白糸連 本町
一層唐破風大屋台
平成元年(1989)建造
施工 寺田建築
彫刻 志村流張
白糸連は大正四年(1915)に諏訪神社祭典に参加、当時は町名も白糸町といった。
寛政元年(1789)に鳥羽山堀割が完成し二俣川の河道が改められるまで、本町付近は二俣川が流れていた。この旧河川敷は、鳥羽山掘削工事を主導した袴田甚衞門喜長によって工事に協力した村民に分配された。
江戸時代の二俣は、古町(旧二俣郷城下村)、新町、中町、横町、二俣川を渡って車道の通り沿いに商家が軒を連ねており、町裏や南部は大半が田畑であったようだ。

明治十七年(1884)に遠州二俣紡績が開業すると、町は「紡績」と呼ばれ、のちに「白糸町」と云うようになった。
二俣紡績は、帝国政府が英国より輸入した当時最新鋭の紡績機を導入した全国十カ所の工場(十基紡)の一つであり、のちのトヨタグループ創始者である遠江敷知郡山口村の豊田佐吉は二俣紡績への就職を希望していたという。
二俣紡績は十年程で廃業したが、二俣町は商業地として発展、白糸町にも人家が増え、明治末頃から諏訪神社祭典参加への機運が高まっていった。

白糸連は大正四年十一月、天皇陛下即位御大典祝祭より旭連と共に諏訪神社神輿渡御に参加した。
年番記録を見ると、当初は旭連、白糸連共に大屋台を有していなかったようである。旭連は大正十年に諏訪連より大屋台を譲り受けた。この時、唯一大屋台のない町となった白糸連は祭典連合からの脱退騒動を起こしているが、翌年に復帰し、大正十四年に大屋台を建造した。
初代の大屋台は白糸町大工遠山鶴雄の作で、柱間四尺五寸と細身に作られた二俣型一層唐破風大屋台。


遠山鶴雄は先代白糸連の他、春野町東領家和田之谷の東和連も建造している。
特徴的な照り起りの美しい二俣型唐破風。

昭和三十一年(1956)に国鉄二俣線「二俣本町駅」が新設され町名は白糸町から本町へ変更された。
昭和後期には転倒事故もあり屋台は老朽化、先代屋台は芳川町大橋芳組へ売却し、寺田建築によって現屋台を平成元年に新造した。


森町の寺田建築はそれまで二輪屋台を手掛けていたが、四輪屋台の建造は白糸連が初であった。


彫刻は福井県三国町の志村流張が刻んだ。

平成三年建造の笠井西魁団も寺田建築、志村流張の作。

昭和二十九年に白糸連から分かれた城下連、昭和三十年新規加入の城南連と共に宵祭りや曳き別れ後も南部三町で連合して屋台行動を行っている。
DVD『諏訪神社祭典 天之巻』『諏訪神社祭典 地之巻』収録!!