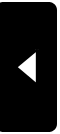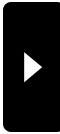2015年03月14日
八幡若連 水窪町奥領家神原 先代八まん連 浜松まつり最古の一層唐破風屋台


八幡若連 水窪町奥領家神原
浜松型一層唐破風大屋台
昭和五年(1930) 浜松市八幡町八まん連建造
大工 岡田五左衛門 豊川市牛久保
彫刻 浦部一郎 浜松市利町(豊橋市出身)
昭和三十五年(1960) 八幡若連へ譲渡
大正十一年(1922)に、五社神社が浜松市の総社となり、それまで季節の風物詩であった濱松名物の凧揚が、初めて五月四日の五社神社祭典と結び付き、祭禮行事として執り行われるようになった。


江戸末期に二俣で曳かれていた屋臺
浜松にも明治末期頃から底抜け屋台が登場してはいたが、江戸時代から屋臺を曳く掛塚や二俣、明治期には本格的な屋臺を建造している(当時は浜松市外で会った)天王や雄踏、遅くとも大正期には本格的な屋臺が登場している笠井や宮口、根堅などに比べると、浜松の本格的な屋台の登場は遅く、昭和の時代を迎えてからである。

昭和五年建造の野口町先代屋台(現・浜北区貴布祢みゆき連)
昭和に入ると、五社神社の神輿は凧揚げ会場まで渡御し、会場からの曳き揚げに際しては総社神輿が先頭で還御し町々の屋臺が続くという神輿還御行列が行われるようになったようだ。
大正十四年の時点で、二俣諏訪神社祭典では十台の大屋臺が諏訪神社神輿に随行する神輿渡御が行われており、当時は浜松からも多くの見物客が二俣を訪れていた。
神輿渡御、還御という神事に随行する屋臺としては、底抜け屋台は具合が悪い。
当時の二俣では、神事である渡御に随行する大屋臺は女人禁制であり神聖な存在で、花屋台(底抜け屋台)で渡御行列に加わることは禁じられていた。また、神輿を二階から見下ろすことは不敬とされていた。
昭和十一年の『静岡民友新聞』には、浜松総社神輿渡御の際「若衆が・・・二階乃至三階から神輿を拝してゐた民家数軒に乱入・・・」とあるのは、二俣の例に倣ってのことであろう。
神輿渡御、還御の神事を始めるにあたって二俣を参考にした、というのは当時の二俣と浜松の経済の結び付きの強さを考えれば自然な成り行きである。その後、二俣も浜松に倣って桃山式二層花屋台を導入しており、相互に影響を与えていたとみてよい。
神輿渡御随行に相応しい本格的大屋臺の建造が望まれたというのは当然の成り行きで、昭和五年建造の八幡町と野口町の一層唐破風大屋台が、その始まりだと云われている。

現存する最古の浜松型重層入母屋造御殿屋台 二俣横町叉水連
昭和八年頃には鴨江町大工三嶽駒吉によって、初めて浜松型重層入母屋造御殿屋台が建造され、次々と大型屋臺が登場する。当時の御殿屋台は女人禁制で、お囃子も異なり、屋臺を威勢良く若衆が曳き廻していたようだ。
残念ながら、戦前の浜松五社神社祭典で曳き廻された豪華絢爛な御殿屋台は浜松空襲で全て焼失。
三嶽駒吉の重層入母屋造御殿屋台は叉水連と春野町西領家坂下紅葉社の二台のみが現存している。

八幡町と野口町の浜松型一層唐破風大屋台も戦禍を逃れ現存している、戦前の浜松五社神社祭典を知る貴重な屋臺である。
重層入母屋造御殿屋台に比べ、一層唐破風屋台は組みばらしが容易であった点が戦禍を逃れた要因の一つかもしれない。
八幡、野口の屋台は共に、豊川市牛久保の岡田五左衛門が建造した。岡田家は三河大工の筆頭であったと云い、江戸時代には立川和四郎と共に仕事をしていたという。
彫刻の浦部一郎は、この頃豊橋から浜松へ移り住み、遠州で最初の仕事が、この八幡と野口の屋台の仕事であったようだ。

昭和十年(1935)浜松鴨江町大工三嶽駒吉建造の浜松型一層唐破風大屋台、天竜区横山町朝日連
浜松型一層唐破風大屋台の特徴は堂々とした大型の唐破風、背は低いが横幅は広い。細部は掛塚の様式よりも二俣に近い、といった点が挙げられる。
戦後、掛塚の屋台大工が御殿屋台建造も多く手掛けたため、いつの間にか浜松の屋台を「掛塚式」などと云うようになってしまったが、本来は浜松独自の形式の屋台であり、重層御殿屋台の祖は浜松鴨江の大工三嶽駒吉であることは忘れてはならない。
また、三河からの影響も掛塚以上に色濃いものであったことを考慮したい。
正式な掛塚型一層唐破風本舞台は、馬込町奴組など数台しか浜松まつりには登場していない。

八まん連では、昭和三十五年に八幡若連に先代屋台を売却後、三年間は屋臺曳き廻しを休止し昭和三十八年に高塚房太郎大工による現屋台を建造。重層御殿屋台では数少ない総漆塗りの屋臺となっている。

みさくぼ祭は、全国的に有名な仮装コンテストもあり、夜の屋台曳き廻しも大変賑やかで露店も数多く出ている。風情のある街並と露店の建ち並ぶ風景は、古き佳き時代の日本の祭りそのものだ。

水窪では女性の小太鼓が左右外側を向いて並ぶ独特のスタイル。
水窪は平家の落人が隠れ住んだ里であり、京美人の遺伝子を受継いでいるので美人が多いそうだ。

屋台がすれ違う際には、お囃子バトルが見られる。
本町若連の屋台も三嶽一郎建造の浜松型一層唐破風大屋台。
DVD『天龍の屋臺』に収録!!
Posted by 天竜北遠のお祭りを応援する會 at 20:45│Comments(0)
│天竜区水窪町