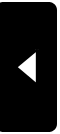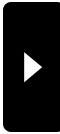2015年02月27日
八幡連 春野町川上 明治二十六年建造の森型屋台 先々代森町北街社


八幡連 春野町川上
御所車型四輪屋台
明治二十六年(1893) 森町北街社建造
昭和五年(1930) 熊切村石内松下共心社が購入し四輪に改造

屋台は森の新町(北街社)が建造し、石内松下共心社を経て現在は川上八幡連が所有。
川上は杉川の上流に位置し川根本町と接する、国道362号沿いでは春野町最奥の地区となる。
春野では、中古屋台を購入するにあたり、下(しも)から上(かみ)へ屋台を持ってくるのは良いが、上から下へ移すのはいけない、という話しをよく聞く。神は山に宿る、という上古の昔からの信仰が生きており、神の依代でもある屋臺を、神のいる山から遠ざけていくのは好ましくないと云うことだろうか。
然し、川上より上流で屋臺を曳いているという話は聞かない。川根では家山に立派な遠州型一層唐破風屋台や豪華なからくり屋台があるようだが、川根本町に屋台があるという情報はない。川上が遠州のどこから中古屋台を買ったとしても、まず下から上に持ってくるということになるだろう(信州にはもちろん屋台は存在する)。

共心社で二輪から四輪に改造したという屋台。
現在は人手不足のため、飾り付けて屋台を出すが、曳き廻しは休止中とのこと。
森型の古い形式を伝える貴重な屋台であるので、曳き廻し可能な状態で保存されることが望まれる。

屋台の前方に小さな出高欄があり、その左右に脇障子という森型独特の形式が既に確立している。

柱には螺鈿が施されている。明治期の春野の屋台では鷹尾連や先代中栄社の柱にも螺鈿で仕上げられている。
こうした古い時代の国産貝を使用した螺鈿細工は貴重だという。

屋台の内側に六本の柱と筋交いが組まれ、天井は一部が吹き抜け。
吹き抜け天井は春野の古い屋台、鷹尾連や北領社などにも見られる。

杉川流域は山香郡与利郷として、平安時代から集落が開けていた。山香郡は川根本町一帯も含む広大な郡であったといい、かつては奥大井との通交も密接であったようだ。
2015年02月27日
八幡社 春野町田河内

八幡社 春野町田河内
御所車型二輪屋台

平成二十六年の祭典当日に田河内住民に聞いた話では、八幡神社祭典は現在神事のみで、屋台は小屋に仕舞われたまま出してはいないとのことであった。
屋台小屋を覗くと飾り付けられた状態であったので、曳き廻しはしないにしても広場に飾ることはしているかもしれない。

森の奥にある八幡神社

田河内は美しい自然に囲まれた天竜川水系熊切川上流の集落で熊切茶の産地、すぐ近くの山が分水嶺となっており、一山越えれば大井川である。
2015年02月26日
共心社 春野町石内松下田黒


共心社 春野町石内松下/田黒
御所車型四輪屋台
石内松下は旧熊切村の中心地。
当地にある熊切小学校は平成二十七年三月で閉校の予定である。
石内松下の氏神は蛭子神明神社で慶安二年(1650)に西宮と呼ばれていた社を蛭子神社に改称したという。昭和三年に神明神社を合祀、蛭子神明神社とした。
神社庁のデータによれば御祭神は
素盞雄命、事代主命、健御名方命、伊弉諾命、伊弉冉命、品田和氣命、天照大神、豊受大神、天忍穂耳命、菅原道真、木花佐久夜姫命
となっている。
何故か肝心の蛭子大神(えびす様)が祀られていない。
昔、西宮と呼ばれていたということで、兵庫県西宮市の「えびす宮総本社 西宮神社」の分かれと思われるが、いつの間にか蛭子大神が抜け落ちてしまったか、元々事代主命を恵比寿さんとして祀っていたのだろうか。
えびすは戎、胡、夷とも書くので、大和朝廷から見た異民族の神を意味するともいう。恵比寿は漁業神であり海から漂着した神であるという。
また蛭子はイザナギ、イザナミが最初に生んだ神とされ、不具であった為に葦の舟に乗せて流されてしまったという漂流する神であり、中世以降恵比寿と同一視されるようになったという。
事代主命と山幸彦(火々出見命)は神話の中で釣りをする場面があるため、この二神も恵比寿と習合していったようだ。
熊切の山中では、大和朝廷に従わず流浪する山の民を戎と見たのだろうか・・・

屋台は大きめの出高欄が付いた御所車スタイルだが、二輪ではなく四輪の山車屋台である。
二輪屋台を四輪に改造したわけではなく、建造当初から四輪屋台である、とのこと。

川上八幡連(共心社先代屋台)
明治二十六年に森町の北街社が建造した先々代屋台を昭和五年に共心社が購入。この時、二輪から四輪に改造したという。
この先代屋台を川上に譲って現屋台を新造するときに、この御所車型四輪屋台のスタイルを踏襲した、ということのようだ。
明治二十二年(1889)石打松下、越木平、筏戸大上、長蔵寺、田河内、田黒、杉、川上、牧野、砂川、胡桃平、大時、花島の各村が合併して熊切村が発足。
明治二十七年(1894)の人口は犬居村3,245 気多村3,068 に対し熊切村は3,490人であった。多くの集落に分散して、かなりの人口が山深い地域に住んでいたようだ。石内松下の街も賑やかであっただろう。
春野町の人口は戦後間もない昭和二十五年に15,187人でピークとなり、現在は5,000人を切っている。熊切地区の人口は、明治、更には江戸時代より少なくなっていると思われる。
「熊切茶」は国産高級茶葉のブランドで、香り、渋み、キレのある力強いお茶、として現在も評判が良いが、旧熊切村は杉川、熊切川、不動川と山を挟んで集落が分散しており、石内松下のような中心商業地は国道からも離れていて、気田や犬居と比べても求心力を失ってしまっているようだ。
DVD『天龍の屋臺』に収録!!
2015年02月25日
八王社 春野町河内 夜川十五七百村と尼子十勇士 山中鹿之助 大谷猪之助


八王社 春野町河内
一層照り破風屋台
河内八王子神社祭典では、古くから奉納相撲があり、神社境内に設けられた「八王子場所」で取組が行われている。
屋台は旧豊岡村から中古で購入したものらしい。

屋台後方の高欄の止めは脇障子ではなく、跳び高欄になっている。

屋台の足回りは軽自動車ベースのようだ。
照り破風の屋根は遠州の屋臺には珍しい。

気田川を挟み、河内の対岸付近には、かつて夜川十五七百村(よかわじゅうごななやくそん)という村があったという。
明治初期の地図を見ると、気田金川辺りにも十五七百の名がある。
氣田の十五七百村(じゅうごななひゃくそん)には、毛利元就に滅ぼされた出雲尼子氏の家来、山中鹿之助が訪れ、悪さをして村人に火あぶりの刑にさらされていた十五歳の少年を銭七百文で買い受け、この少年がのち猪を素手で捕らえ大谷猪之助の名を与えられ尼子十勇士となったという逸話がある。
夜川の十五七百村にも、これと似た話があり、尼子十勇士の一人大谷古猪之助(大谷猪之助と同一人物と思われる)が十五歳の少年を七百文で買ったから、その名が付いたという。

十五七百はまた、「キイナゴ」と読んだ、ともいう。
明治九年(1876)に河内村、高瀬村、久保田村、里原村、平木村、夜川十五七百村が合併して宮川村となった。
その後、夜川十五七百の集落は水害で消滅してしまったという。
DVD『天龍の屋臺』収録!!
2015年02月24日
大谷連 大谷 宇佐八幡大神は、天磐船に乗って磐田之海をやって来た


大谷連 大谷
一層唐破風大屋台
平成二年(1990)建造
上古の昔、まだ二俣郷が磐田之海であった頃、神は天の磐船に乗ってやって来た。


宇佐八幡大神は天の磐船でやって来たが、船は嵩山に激突、転覆し嵩山の行者岩には大穴が開いた。

大穴の残る行者岩。その名の通り、この穴には役行者が祀られている。
船が沈んだ宇佐八幡大神は、行者岩の下に鎮座することとなった。

大谷宇佐八幡神社に古くから伝わる金鳴石は中国から渡来したという。叩くと本当に金属の音がする。



行者岩の上からは北は船明ダムと赤石山脈の山々、南は大谷の家並み、彼方に遠州平野が一望出来、アクトタワーまで見渡せる。
行者岩は二俣地溝帯上部礫岩という地層の一部であり、同様に役小角が祀られる烏帽子山、清瀧寺、栄林寺、毘沙門にこの地層が露出しており、古くからの奇岩崇拝、磐座信仰がそのまま後世の神社や寺院の信仰に繋がっていったことがわかる。


嵩山行者岩から尾根伝いに山東へ向かえば金光明山光明護国禅寺奥之院に至る。
この地は、養老元年(717)から翌年にかけて光明山、春埜山、秋葉山の遠州三山を開創したと伝わる行基菩薩が最初に訪れた地とされる。
嵩山(たけやま)という名にあるように、古代の人々はこの山を崇高な聖山として信仰の対象にしていたのだろう。

光明山奥之院からは、二俣郷、そして磐田之海と呼ばれた遠州平野が一望出来る。
戦略拠点に相応しい眺望であり、七千五百の大眷属を引連れ遊現した遠州の山の支配者、光明笠鋒坊大権現になぞらえるような強大な権力者がこの地に君臨していた可能性は高い。

強大な権力者が埋葬された浜松市最大の前方後円墳、光明山古墳は光明寺正面にある。

大谷にある内山真龍資料館

内山真龍は遠江國豊田郡二俣郷大谷村出身の国学者、『出雲風土記解』『遠江國風土記傳』など重要な著作を残し、『日本紀類聚解』は朝廷に献上し天覧を得た。天覧の例は本居宣長など真龍を含め三例しかない快挙であるという。
DVD『天龍の屋臺』収録!!
2015年02月24日
旭連 旭町


旭連 旭町
透漆塗欅造一層出組唐破風大屋台(後輪外車)
昭和五十七年(1982)建造
大工 伊藤賢太郎
彫刻 雨宮国雄 稲毛好太郎 伊藤章晴
旭連は大正四年より二俣諏訪神社祭典に参加。
当時は町名を毘沙門と云ったが、二俣で最も東の町(当時、阿蔵は諏訪神社祭典に参加していなかった)として朝日の昇る町「旭連」を連名とした。同時加入の白糸連と共に、当初は大屋台を有していなかったが、大正十年に屋台を新造した諏訪連より先代屋台を譲り受けた。その後、町名も毘沙門から旭町に変更されている。

水ヶ谷連(先代旭連、先代諏訪連)
先代旭連大屋台は磐田市大藤五豊社を経て天竜区へ戻り山東水ヶ谷連が所有。
腰高欄縁葛の支えが組子ではなく持ち送り、脇障子が非常に長く細い、二段欄間であるなど二俣型一層唐破風大屋台としては最も古典的な要素を持っており、最古の二俣型一層唐破風大屋台ではないかと考えられている。
旭連では、大藤にこの屋台を売却後も毎年のように曳き廻しを手伝いに行くなど強い愛着を持っており、また、多くの屋臺ファンがこの屋臺に関心を寄せていたため、大藤から天竜区へ帰還する際には大勢のギャラリーが詰め掛け、二俣郷への里帰りを見守ったという。

とはいえ、勇壮豪快な屋臺曳き廻しで知られる二俣諏訪神社祭典において、屋台の老朽化は問題となり、昭和五十七年に豊岡大楽地の大工、伊藤賢太郎により屋台が新築された。

屋台の特徴としては、唐破風屋根の組子(斗栱)が出組(一手先)となっている点や、浜松御殿屋台に見られるように後輪が外輪になっている点がある。二段欄間(1.5段?)は先代を踏襲している。
側面の欄間彫刻は旭町在住の稲毛好太郎の作。

芳川町大橋芳組 遠山鶴雄作先代白糸連
大正十四年白糸町大工遠山鶴雄が先代白糸連を建造、この時、若き日の伊藤は建造を手伝っていたという。
伊藤大工の屋台造りは出組唐破風、後輪外車といった特徴的な部分を除けば、概ね二俣型大屋台の伝統を受け継いでいる。
旭連大屋台は二俣型屋台の系譜として良いかもしれない。なお、旭連大屋台は伊藤賢太郎大工の遺作となった。

木鼻彫刻は三ヶ日の伊藤章晴が手掛けており、生命力漲る力強い獅子が刻まれている。
欅を多用した屋臺は随所に美しい杢目を魅せている。

雨天時には先代屋台に使用していた水引、見送り幕に替えている。
屋台建造間もない昭和六十年、旭連は七福神を描いた美麗な見送り幕を新調したが、同年発電機火災により幕を焼失、屋臺も被害を受けたが、翌年には大改修を施し諏訪神社祭典に参加している。

神田諏訪連

新開新若連
豊岡大楽地在住の伊藤大工は豊岡で多数の屋臺を建造している。
腰高欄の手摺りは低く抑えられ前方のみ擬宝珠がつく、など二俣型屋台の特徴に則った屋台造りが見られる。

於呂中沢組 昭和五十七年建造

貴布祢西町組 昭和五十八年建造
中沢組建造中に急逝した伊藤賢太郎氏の意志を引き継ぎ、息子の伊藤肇氏が建造した浜北の中沢組と西町組。
高欄は手摺りが高くなり中擬宝珠が付けられるなど二俣型の特徴は薄れている。

毘沙門堂
旧町名の由来となった毘沙門堂は栄林寺の堂宇で、建徳元年(1370)創建、毘沙門天像は行基菩薩作と伝わる。
徳川家康は二俣城奪回戦(1575)において毘沙門の山手に毘沙門堂砦を築き本多忠勝が布陣した。
また、かつて左甚五郎作の竜の彫刻が奉納されていたが、火災により焼失してしまったという。

いぼ取りに御利益があるという毘沙門堂地蔵菩薩は、大変な子供好きだという。
ある時、子供達がお地蔵様に縄をかけ引きずり回して遊んでいた。それを見た近所のお婆さんが「罰が当たる」と言って子供達を咎めたところ・・・その夜、お婆さんは高熱が出て寝込んでしまい、お地蔵様が現われて「せっかく子供らと楽しんでただに邪魔したで婆に罰をくれたでねぇ」と云ったという。

東谷山栄林寺
貞治四年(1365)開創の曹洞宗寺院、遠江四十九薬師霊場第二十九番札所

クリスマスが近づくとイルミネーションでライトアップ。
住職がサンタクロースに扮してクリスマスを祝うお寺としてテレビ朝日「ナニコレ珍百景」でも取り上げられた。
栄林寺は以前、保育園を併設しており、子供達を楽しませることと日没の早い十二月に周辺道路を明るく照らす目的でこうした行事を行っているという。


栄林寺には二俣地溝帯上部礫岩という地層が露出している。この岩石層は毘沙門、清瀧寺、烏帽子山、大谷行者岩に見られ、古代から磐座信仰の対象となっていたようで、現在も全ての地点に何らかの信仰対象が鎮座している。
こうした奇岩信仰が遠州山岳修験の基本となっているようだ。

二俣から毘沙門へ渡る上竜橋は、明治十一年(1878)に初めて長さ八十一メートルの木橋が架けられたが洪水で流失や破損があり、明治十三年の修繕後、双龍橋と名付けられた。明治三十九年に全長七十メートルの橋に架け替えられたが、相変わらず板橋であり、旭連が諏訪神社祭典に参加した以降、各町の屋臺は、幅二間の橋を恐る恐る渡っていくことになる。
この為、橋を渡るときは、静かなお囃子を奏でゆっくりと渡るようになり、現在でも橋を渡るときは「流し」や「深囃子(ザーザー)」などにお囃子を切り替える習慣が残っている。
昭和十六年の洪水で双龍橋は流失し、新たに架けられたが、翌年百メートルほど下流に双龍橋が新設され、元の橋を上竜橋と呼ぶようになり現在に至っている。
栄林寺前の二俣川は遊歩道や飛び石橋が整備され、夏場は川遊びの子供達で賑わっている。
DVD『諏訪神社祭典 天之巻』『諏訪神社祭典 地之巻』に収録!!
2015年02月23日
笹若連 笹岡


笹若連 笹岡
二俣型一層唐破風大屋台
昭和二十四年(1949)建造
大工 鶴田多一 伊藤秀次 清水重雄
平成二年(1990)改修
戦後間もない昭和二十四年に諏訪神社祭典へ新規参加となった笹若連は、まだ物資の不足する時代に地元青年らが中心になって屋臺を完成させた。
小型軽量の屋台は、動きの激しい二俣の屋台の中でも一段と際立った高速の曳き廻しをみせ見物客を楽しませている。

建造にあたった大工は腕の良い指物師で、彫刻の代わりに随所に精緻な指物細工を施している。
かつては二俣にも、こうした一級の指物職人がいたものだが、伝統的な技法は徐々に廃れてしまっており、今となっては、非常に貴重な飾り細工となっている。

高欄は改修時に変更されているが、オリジナルは腰高欄には珍しい「跳び高欄」になっていた。
腰板の額縁も、二俣型大屋台の伝統に則った非常に凝った意匠をしており、二俣らしい美しい照り起りの唐破風や流麗な細身のフォルムなど、非常に良く整った端正な屋臺となっている。
小型の屋臺である故、何度か屋台新造の話もあったようだが、このように丹精込めて緻密に作り込まれた屋臺への愛着は強く、笹岡住民にとって自慢の屋台となっている。

笹岡古城
現在天竜区役所がある本城山には中世城館の笹岡古城が存在していた。
二俣郷は笹岡、大谷、八幡の二俣川北岸と上市場(栄町と山王西部、二光滝が出来る以前は、二俣川南岸であった)周辺に最初の集落が形成されていったようだ。
車道の烏帽子山や大谷の嵩山には、神が天の磐船に乗ってやって来たという天孫降臨伝説があり、嵩山の山東側には浜松市内最大の前方後円墳である光明山古墳が築かれている。
上市場、田組には古墳時代から鎌倉時代にかけての遺構が多数発見されているという。この二俣北部、山東西部一帯が国衙領磐田郡山香郷に比定されており、平安時代後期から室町時代後期まで山香郷(鎌倉時代には二俣郷と呼ばれるようになっていたようだ)の政治的中枢を担っていたのが笹岡城(二俣古城)であったようだ。
笹岡古城の守護であったのは、大谷宇佐八幡神社であった。現在、光明寺のある嵩山から笹岡本城山、蜷原、二俣城のある城山までは尾根伝いに行くことが出来る。古くは光明山(鏡山)とも一体の山であったと思われ、戦乱の時代に笹岡周辺は戦略上重要な位置を占めたのではないだろうか。

二俣の名が最初に文献に見えるのは『吾妻鏡』文治二年(1186)四月二十一日に安田義定(1134-1194、源義家の弟、新羅三郎義光の孫か曾孫にあたる、富士川の合戦の戦功により遠江國守護となった)が二俣山で捕らえた九頭の鹿革を源頼朝、若君、小山七郎朝光に送ったとの記事がある。
源頼朝は小山朝光の烏帽子親であり、小山朝光は結城家の家祖として結城七郎朝光(1168-1254)ともいう。
内山真龍は『遠江國風土記伝』において、笹岡城の南に「ゆき殿之谷」の字が残るところから、笹岡城を築いたのは結城七郎朝光ではないかと推測している。
また一説には、二俣五郎太夫、二俣弾正(二俣近江守昌長の遠祖と思われる)が嘉保元年(1094)に二俣城(笹岡城か?)を築き居城したという。
源頼朝の弟、源範頼は遠江國蒲出身であり、頼朝が挙兵した伊豆に近い遠江は初期の鎌倉幕府にとって重要な拠点であり、天険の要害である二俣が重視された可能性は高いのではないだろうか。

天神山長光寺
長興寺の名は康正三年(1457)が初見だと旧天竜市のホームページにあるが出典不詳。
この頃の遠江守護は斯波義敏(1435-1508)で、その子の遠江守護代斯波義雄(生没年不詳)が豊岡の社山城で駿河の今川氏と戦って敗れ、二俣城に退いている。斯波義雄が城主となった二俣城とは笹岡古城のことであるとされる。
この時点では、尾張に本拠を持つ斯波氏の対今川の前線基地が二俣城になっていたようだ。
なお、今川家臣である二俣近江守昌長が、今川氏親によって社山城から二俣城へ移されたのが文亀三年(1503)とされるので、この頃には二俣城も今川傘下となっていたようである。
長光寺は寺伝によれば栄林寺末として文禄元年(1592)の開創と伝わっている。

長光寺の聖観音菩薩像
笹岡城の西に位置する長光寺は旧くは観音堂と呼ばれたようだ。

陸軍中野学校二俣分校跡地
陸軍中野学校二俣分校は、大東亜戦争末期の昭和19年に遊撃隊幹部養成を目的に開設され、短期間のうちに非常に高度で濃密な軍事教育が行われた。一期生(俣一会)には情報将校として最後まで戦争を戦った小野田寛郎少尉らがいる。
DVD『諏訪神社祭典 天之巻』『諏訪神社祭典 地之巻』に収録!!
2015年02月23日
白山連 二俣町阿蔵


白山連 二俣町阿蔵
掛塚型一層唐破風本舞台
昭和二十六年(1951)建造
大工 小池佐太郎
彫刻 奧出多喜男 奧出文男
昭和五十三年(1978)総漆塗

阿蔵山久延寺
遠江國豊田郡二俣郷阿蔵村は、阿蔵山久延寺がある阿蔵川上流、阿蔵谷周辺に切り拓かれた三十戸ほどの集落で、二俣郷諸村が概ね幕府直轄領であったのに対し、阿蔵村は掛川藩領であった。
阿蔵村の水田には条里制地割の痕跡も認められるといい、阿蔵の村名には穀倉地帯という意味もあるようだ。
阿蔵山久延寺は朱符之寺田高二十石を今川氏によって安堵されており、古くは雲谷山九淵寺と称し二俣城主二俣近江守昌長(?-1551?)が和田(現在の本町、城下町付近)に開基、天正年間(1573-1593)に阿蔵へ遷ったという。
当初、二俣城下(和田)にあった当初は霊長山の山号であったとの説もある。
二俣川下流域の鳥羽山麓付近には油淵という大きな淵があった。九淵寺の由来と関係あるのだろうか?
遠江二俣氏は菅原道真(845-903)に仕えており、道真左遷の際に遠江に移り住んだという。また、源八幡太郎義家(1039-1106)が遠江國府(見付)に逗留した際、土豪二俣五郎太夫の家に宿泊したされる。また一説には義家の願により横地家永家臣二俣弾正が菊川横地の藤谷大明神造営に携わったという。菊川横地には今も二俣姓が残っているようである。
一説に二俣五郎太夫、二俣弾正が嘉保元年(1094)に二俣城(笹岡城か?)を築き居城したという。
二俣昌長の後裔は伊予國(愛媛)今治に移り住んだといい、現在天竜区二俣には二俣姓の子孫は残っていないようだ。

八握神社
戦前までは阿蔵独自に二輪屋台を曳き廻し八握神社の祭禮を行っていたという。
村内には宇佐八幡神社と白山神社も祀られていたが、明治初期の一村一社令に基づき両社を八握神社の境内社とした。昭和十六年、この白山、宇佐八幡両境内社を八握神社に合祀している。
連名の白山連は、このうちの白山神社に因んで名付けられた。

豊田郡阿蔵村は明治二十二年、二俣村他三村と合併し豊田郡二俣町阿蔵となった。
昭和五年(1930)光明電気鉄道二俣口駅開業
光明電鉄は新中泉(現JR磐田駅構内)から二俣町(現天竜協働センター付近)一日十四往復、最短37分で結ぶ、当時としては画期的な電気鉄道であったが、船明まで延伸し材木や鉱山の貨物輸送による増収(二俣町から新中泉経由で東海道線へ連携運輸する貨物の取り扱いが昭和六年から行われていた)を見込んでいたものの資金繰りが悪化し全線開通を果たせず昭和十年には経営破綻した。

光明電鉄二俣口駅の残存するプラットフォーム

昭和十五年(1940)国鉄二俣線遠江二俣駅開業
光明電鉄廃線後、東海道本線の迂回路として国鉄二俣線の建設が急ピッチで行われ、一部光明電鉄廃線跡を利用して開通した。実際に大東亜戦争中には東海道線が何度か普通になり、特急列車が二俣線を通過することもあったようだ。
遠江二俣駅の置かれた阿蔵は二俣町の玄関口として発展した。

昭和四十二年(1967)国鉄佐久間線着工
阿蔵地内にも白山トンネル、阿蔵川橋梁が建設された二俣線遠江二俣駅と飯田線中部天竜駅を結ぶ予定の国鉄佐久間線であったが、国鉄再建法により昭和五十五年には工事が凍結、未完のまま計画は中止された。
平成十三年の飛龍大橋開通に伴い、国道152号線浜北天竜バイパスの飛龍大橋以北部分の建設が阿蔵山で進められている。


昭和二十六年より二俣諏訪神社祭典に参加することとなった白山連は、同年、車道から阿蔵まで神輿渡御の先駆を勤めている。翌二十七年から現在に至るまで車道から御旅所大明神までの先駆は南がく連が勤めることになっている。
屋台は小池工務店の建造による掛塚型一層唐破風本舞台だが、町内回りの関係で、やや小さめに作られている。
力感のある彫刻は阿蔵に在住していた奧出多喜男、文男父子によるもの。
奧出多喜男氏は愛知県名古屋市中村区花車町出身の堂営彫刻師で、戦後二俣に移住。白山連を皮切りに遠州の屋台に彫刻を刻み名声を得ている。
花車町の先代二福神車は、江戸時代から明治中期に二俣㡌山連が曳き廻し、現在宮口研精社が所有する三階屋台であり、花車町と二俣には祭りを通じた縁があるようだ。
DVD『諏訪神社祭典 天之巻』『諏訪神社祭典 地之巻』収録!!
2015年02月22日
下若連 只来下組 下只来


下若連 只来下組 下只来
二俣型一層唐破風大屋台
昭和二十四年(1949)建造
大工・彫刻 北島俊二

只来(ただらい)六所神社祭典で曳き廻される下若連大屋台は、山東八幡、二俣車道に住んでいた大工北島俊二の手による二俣型一層唐破風大屋台。
最後の二俣型屋台大工となった北島は下若連、相生連、城南連(現浜北区中瀬仁久連)、南栄連大屋台と白糸連、吾妻連の花屋台を手掛けた。

彫刻も北島大工の手によるもの。
元々宮大工ではなく一般建築を手掛けていたという北島大工だが、笛の名手でもあり能管で「狂言鞨鼓」なども難なく吹いていたという器用で芸達者な人物であったという。

二俣型大屋台の特徴である、丸みを帯びた唐破風、前方のみに擬宝珠がつき手摺りの高さが低い腰高欄、細く長い脇障子、全体的に細身のフォルムなどをしっかりと受け継いでいる。

下若連大屋台では腰高欄の縁葛を支えているのは組子ではなく持ち送りで、最古の二俣型一層唐破風大屋台である水ヶ谷連(先代諏訪連→先代旭連)へのオマージュも込められているのだろうか・・・?
北島大工が手掛けた二俣型一層唐破風大屋台は以下の通り

相生連 昭和二十六年

城南連(現仁久連) 昭和三十年

南栄連 昭和三十三年
上記四連共にDVD『二俣諏訪神社祭典 地之巻』『天龍の屋臺』に収録!!
2015年02月21日
籠城連 上若連 上只来


籠城連 上若連 上只来
一層唐破風屋台

只来六所神社
天竜区只来(ただらい)は光明山遺跡のある鏡山麓に位置する集落。
上只来籠城連(上若連)と下只来下組(下若連)の二台の屋台が曳き廻される。
六所神社の社殿は非常に立派な造りである。


光明山遺跡から磐田方面を見渡すと、上写真右下に見えるのが只来の集落で、鏡山山頂の光明寺を含め東は只来まで、北は山中までが二俣郷であった。
戦国期の只来は今川家臣松井氏の居城である二俣城と天野氏の勢力である犬居城の中間に位置しており、享禄年間(1528~32)に今川家臣朝比奈時茂が鏡山山頂に光明城を築いた。この時、鏡山にあった光明寺は山東に遷っている(光明寺は江戸初期に鏡山に戻り、昭和初期に火災に遭って再び山東の現在地に遷された)。
そして戦国時代末期、武田勢と徳川勢が激しい攻防を繰返した頃には、山麓の只来にも只来城が築かれた。

光明山遺跡
現在残る石垣は、江戸期以降の光明寺の遺構と思われるが、光明城もこの付近に築かれていたようだ。

光明城からは遠州平野が一望出来る。
写真中央右は浜名湖、左手前の盆地が二俣。敵が攻めてくれば、烽火を上げて二俣城や只来城に指示を飛ばしたり、後方の秋葉山頂に築かれた秋葉城とも連携出来る。
光明山や秋葉山は平時には山岳信仰の霊場となっているが、戦乱の時代には軍事拠点として使われている。光明、秋葉ともに戦の神としての側面も持っている。

銘菓『光明勝栗』の由来
天正三年(1575)光明城の武田軍は徳川家康の軍勢に夜襲をかけようと企てたが、光明寺和尚が家康にこのことを注進。横川から光明山に登った徳川軍は赤豆坂(あずきざか)で武田軍を撃破。
この時、山東と只来の農民が家康に茶菓として搗栗を献上、家康は「功名(高名)勝栗」に繋がると大いに喜び、農民達に苗字帯刀を許した。爾来『光明勝栗』は幕末まで三百年近く将軍に献上され、山東、只来両村は庸役が減免されていたという。
DVD『天龍の屋臺』収録!!