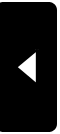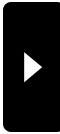2015年02月21日
籠城連 上若連 上只来


籠城連 上若連 上只来
一層唐破風屋台

只来六所神社
天竜区只来(ただらい)は光明山遺跡のある鏡山麓に位置する集落。
上只来籠城連(上若連)と下只来下組(下若連)の二台の屋台が曳き廻される。
六所神社の社殿は非常に立派な造りである。


光明山遺跡から磐田方面を見渡すと、上写真右下に見えるのが只来の集落で、鏡山山頂の光明寺を含め東は只来まで、北は山中までが二俣郷であった。
戦国期の只来は今川家臣松井氏の居城である二俣城と天野氏の勢力である犬居城の中間に位置しており、享禄年間(1528~32)に今川家臣朝比奈時茂が鏡山山頂に光明城を築いた。この時、鏡山にあった光明寺は山東に遷っている(光明寺は江戸初期に鏡山に戻り、昭和初期に火災に遭って再び山東の現在地に遷された)。
そして戦国時代末期、武田勢と徳川勢が激しい攻防を繰返した頃には、山麓の只来にも只来城が築かれた。

光明山遺跡
現在残る石垣は、江戸期以降の光明寺の遺構と思われるが、光明城もこの付近に築かれていたようだ。

光明城からは遠州平野が一望出来る。
写真中央右は浜名湖、左手前の盆地が二俣。敵が攻めてくれば、烽火を上げて二俣城や只来城に指示を飛ばしたり、後方の秋葉山頂に築かれた秋葉城とも連携出来る。
光明山や秋葉山は平時には山岳信仰の霊場となっているが、戦乱の時代には軍事拠点として使われている。光明、秋葉ともに戦の神としての側面も持っている。

銘菓『光明勝栗』の由来
天正三年(1575)光明城の武田軍は徳川家康の軍勢に夜襲をかけようと企てたが、光明寺和尚が家康にこのことを注進。横川から光明山に登った徳川軍は赤豆坂(あずきざか)で武田軍を撃破。
この時、山東と只来の農民が家康に茶菓として搗栗を献上、家康は「功名(高名)勝栗」に繋がると大いに喜び、農民達に苗字帯刀を許した。爾来『光明勝栗』は幕末まで三百年近く将軍に献上され、山東、只来両村は庸役が減免されていたという。
DVD『天龍の屋臺』収録!!
Posted by 天竜北遠のお祭りを応援する會 at 15:35│Comments(0)
│光明