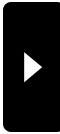2015年02月03日
西煙火連か組 西鹿島


西煙火連か組 二俣町西鹿島
一層唐破風大屋台(三谷型改造)
安政三年(一八五六)三河國宝飯郡三谷村仲屋敷建造
大正十三年(一九二四)浜名郡赤佐村根堅大門購入改造
平成元年(一九八九)天竜市二俣町西鹿島購入
平成二十年(二〇〇八)西鹿島太田良彦大工による復元新調

椎ヶ脇神社


鹿島八幡宮
二俣郷社椎ヶ脇神社の祭典は八月二十日に行われ、天竜川に浮かべた舟屋台に神輿を載せ北鹿島へ渡御すると倶に、奉納煙火を打ち上げた。神輿が渡った北鹿島御旅所では、その夜氏子一同が泊まり込む御夜籠りが近年まで古式ゆかしく行われていた。明治十二年の二俣郷社椎ヶ脇神社所属は、二俣村五百五拾四戸、大谷村拾八戸、大園村拾九戸、阿蔵村三拾五戸、鹿島村七拾五戸、合計五ヶ村七百壱戸となっている。
奉納煙火は明治十一年郷社椎ヶ脇神社祭典で筒径三寸五分、玉数十五本、合薬弐貫目とあり、明治十三年二俣村社諏訪神社祭典奉納煙火の筒径三寸五分、玉数十五本、合薬壱貫五百目と大して規模の変わらないものであったようだが、諏訪神社の奉納煙火は明治三十三年で中止されたのに対し、椎ヶ脇神社祭典奉納煙火は大正頃には、「日本一、天下の名物 鹿島の花火」と称するほどに盛大になっていった。
深夜十二時から弐尺玉を連発し、その花火の下、天竜川を神輿を載せた舟屋台が渡御する壮大な神事となり、「日本三大花火」に数えられ、大正以降は村社諏訪神社祭典も郷社祭典に合わせ八月二十一、二十二、二十三日に変更して行われ全国から観光客を集めていた。
明治三十四年、「鹿島区民山車屋台新調し無交渉にて車道町まで進行せり」と二俣町祭典年番係の記録にあるが、おそらく北鹿島が所有したと思われる、この山車屋台の行方は不明。
花火の打ち上げは、西煙火連と北煙火連の若連で行っていたが、昭和後期から専門の花火師が行うようになり、末期には北煙火連が鹿島橋歩道橋を歩いて渡っていた神輿渡御も途絶え、観光イベント化した鹿島の花火は椎ヶ脇神社祭典とは完全に切り離された。その後、鹿島地区の祭典は椎ヶ脇神社と鹿島八幡宮の祭禮となり、神輿渡御は西煙火連が引き継ぎ、現在は椎ヶ脇神社から屋臺を供奉させて鹿島橋を渡し北鹿島御旅所に渡っている。
DVD『天龍の屋臺』、『二俣諏訪神社祭典 地之巻』収録
Posted by 天竜北遠のお祭りを応援する會 at 08:58│Comments(0)
│天竜区二俣町